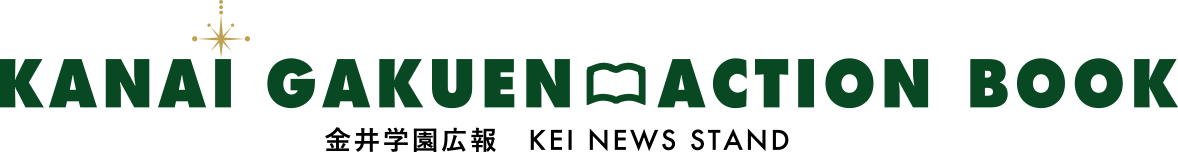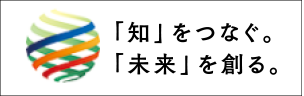***
福井工業大学 AI & IoT センター は、令和3年12月15日(水)15:00から大学2号館8階2-802教室において講演会を開催。
学外からは県内を中心としたIT関連事業所の皆さま、学内はセンター関連教員、工学部電気電子工学科と環境情報学部経営情報学科でソフトウェア工学を学んでいる学生さんなど約110名の皆さんが対面とオンラインで参加し、ユーザ企業とエンジニアの共創によるソフトウェア開発と、AIを用いた新規事業開発についての講演を熱心に聴講しました。
■講演内容
(講演1)
演題:ユーザとエンジニアの共創によるシステム開発 〜アジャイルと Scrum〜
講師:株式会社永和システムマネジメント 代表取締役社長 平鍋 健児 氏
(講演2)
演題:AI & IoT を使った新規事業の取り組み
(1) 福井大学医学部と共同研究中の「AI 患者」
(2) キノコ成長分析(画像認識)/来店人数予測システム(データ分析)
(3) 介護施設向け AI&IoT を活用した排泄時期予測システムの実証
講師:株式会社永和システムマネジメント 医学教育支援室 シニアエキスパート 竹内 清一 氏
***
.
.
■はじめに
講演会に先立ち掛下知行学長が挨拶。大学の研究活動とAI &IoTセンターの概要について説明し、講演を引き受けてくださった講師お二人へ謝辞を述べました。
***
■講演1
続いて、お一人目の講演となる平鍋 健児 氏。金融システム、医療システム、組み込み技術、管理部、アジャイル事業部、ITサービス事業部、医学教育支援室といった部門を抱える永和システムマネジメントという会社や、アジャイル開発に関わってこられたこれまでの経験についてお話頂きました。※補注参照
参加している学生たちには、「現代社会においてソフトウェアは産業の米。すべての産業の基本となっている。君たちはプログラミングが出来ることが大変な強みになる。今や様々なビジネスとITがつながっている。それにデータはオイルだ。データが扱えないとビジネスは動かない。
ソフトウェアエンジニアは地方でも海外へ出ても活躍できる時代。科学技術の進展のスピードが速く未来も不確実な時代においてはユーザとエンジニアが共感・共創しながらシステム開発をし、良い関係づくりをすることが大切だ。従来の考え方から脱却して試行することで価値の変化に敏感に対応しよう。」と軽快な口調で話をしてくださいました。
これからソフトウェア開発の世界で生きていこうとしている学生たちにとって、平鍋氏のお話はとても刺激的で魅力的だったと思います。
***
.
.
■講演2
二人目の講演者は、同じく永和システムマネジメント医学教育支援室シニアエキスパートの竹内 清一 氏。ここ2〜3年取り組んだAI&IoTを使った新規事業について目的ベースでの内容をお話しされました。長いキャリアを積まれてきた後、2018年から機械学習に興味を持ち始め、福井大学医学部との共同研究によるAIを使った模擬患者に対してOSCE(医療面接)をのIT化に取り組んだ事例や、キノコ成長分析、来店人数予測システムなどの開発などの事例を紹介。
現在は、経産省の事業として介護施設の入所している要介護者の方の排泄のタイミングを予測するAIシステムの開発に取り組んでいるとのことでした。日本が抱える最大の課題の一つである超高齢化社会の到来を前に、介護分野の業務のネガティブなイメージを軽減するための事業であり、たくさんの方々に励まされて、大変やりがいを感じながら取組んでいると強調されました。確かにユーザそれぞれに寄り添い、実に多岐に亘る事業に取り組まれておられていることに驚きます。
***
.
.
■講演をお聴きして
ITは外に外注する時代から社内でエンジニアと共に、常に新しいニーズに沿って創っていくことが求められています。そして、どんなに情報技術が進んでも、最後には人のチカラが大切。「お客様と美味しい食事を食べることが理想です。」と平鍋社長。お二人の講演からもそんなお人柄が感じられる講演会でした。 金井学園広報
***
.
※補注(講演概要としていただいた事前資料より転載)
ビジネス環境の変化とデジタル技術の進歩によって、いま、ソフトウェア開発が大きく変化しています。その1つは、アジャイル。ビジネスとエンジニアがワンチームで開発を進めます。
esm(永和システムマネジメント)でも、2018年から福井にアジャイルスタジオを開設し、ビジネス展開をしています。もう1つが、AIです。これまでは人間がロジックをプログラム化していましたが、膨大なデータと計算機パワーを利用して、AIがデータから特徴量を抽出し、その特徴量に基づいて分析や予測を行うことで、人間と同等の成果を出せる場面が具体的に登場してきました。esmでもAI関連の技術革新に伴い高度に整備されたプログラミング環境を利用して、様々な社会課題にAIを適用しています。
アジャイルもAIもともに正解が最初にあるわけではなく、仮説検証型の繰り返しのプロセスと、最終的には人の感覚的な力も見直されてきたのだと思います。本講演では、アジャイル開発の考え方や事例、および、AIの活用事例を具体的にお話し、みなさんが、エンジニアとして福井や日本、そして、世界で活躍できるような未来を想像するお手伝いができたら、と思います。
□ □ □
リンク|「知」をつなぐ。「未来」を創る。|福井工業大学AI &IoT センター 公式ウェブサイト
.

講師お二人と掛下学長・芥子AI &IoTセンター長